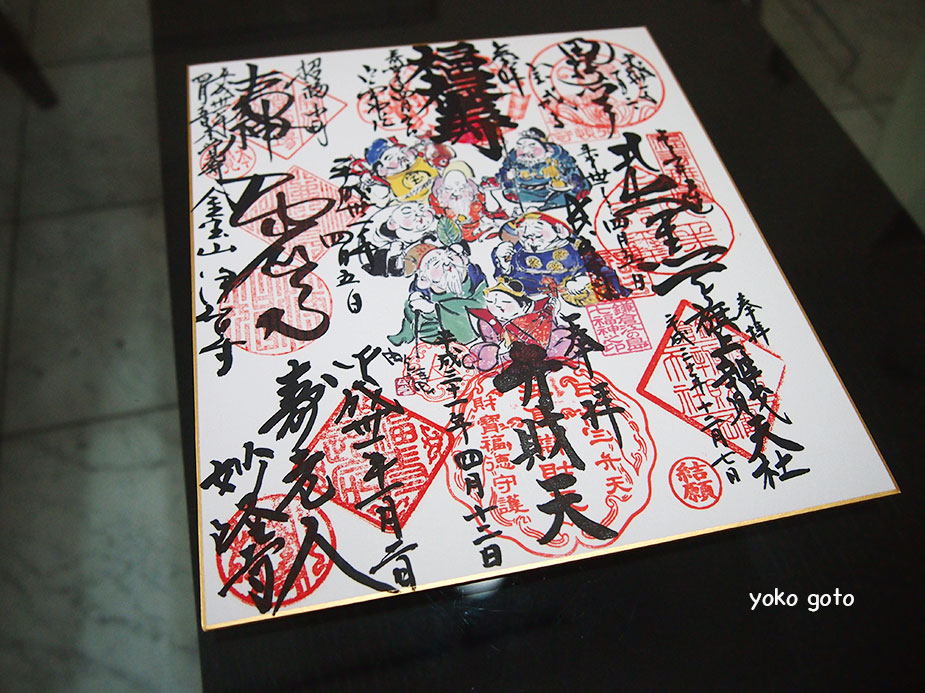*本記事はアフィリエイト広告を利用しています。

6月の鎌倉 明月院は外せない紫陽花スポットだよ
プロフィール

社歴28年のデザイン会社(オフィシャルサイトはこちら)を経営しています。本ブログはプライベートのあれこれを綴った雑記ブログです。特に、週末でかけた観光スポットを、記事と動画でご紹介していますので、ぜひ御覧ください。
YouTube動画(紫陽花の季節の明月院を動画でご紹介)
四季のある日本では移りゆく季節ごとに、さまざまな草花たちの息吹を感じることは、このうえない贅沢です。
2月は梅、3月は桜、4月から5月にかけては、ハナミズキや木蓮。
とりわけ、春から初夏にかけて咲く花々たちは、私たちの心踊らせ日本中を美しく染めていきます。
そして6月。
この時期にさく紫陽花もまた美しく、梅雨の鬱陶しい気持ちを中和してくれるようです。
6月に満開を迎える紫陽花は日本各地で名所と呼ばれるスポットが沢山あります。そして、古都鎌倉は数多くの紫陽花の名所があるエリアです。
鎌倉には『あじさい寺』とも呼ばれるお寺がいくつかあり、なかでも有名なのが長谷寺や明月院です。
長谷寺は坂東三十三観音霊場でもあり、外国人も多く訪れるスポットで、見どころ満載のお寺ですが、このブログでは、明月院の紫陽花について書いています。満開の紫陽花の様子をYouTubeにもアップしましたので、上記のYouTubeを御覧ください。
鎌倉『明月院』は北鎌倉より歩いて10分くらいの所にあるお寺です。(臨済宗建長寺派)正式には『福源山明月院』といいます。北鎌倉駅から明月院までの道の途中にあるお寺『浄智寺』の向かいの谷のことを『明月谷』といいます。そこから、この名前がきているようです。
明月院は、いまでは廃寺となっている禅興寺の塔頭(禅宗寺院の敷地内にある小寺院や別坊)として成立したお寺でした。
明月院の創建は今から約850年前にかさのぼります。平治の乱において、この地で戦死した武将、山内首藤利通の菩提供養のために、俊道の子である山内首藤経俊が創建しました。
それから、約100年後、第5代執権北条時頼が出家のために最明寺を建立しましたが、時頼の没後に廃絶。その子である、第8代執権の時宗が、その最明寺跡に『禅興寺』を創建したそうです。
その後に、上杉憲方が寺院を拡大。この時に、明月庵は明月院と改められました。
その後、禅興寺は明治初年に廃寺となってしまいましたが、明月院だけを残し、今に至るそうです。
そして、北鎌倉駅から明月院までには有名なお寺が多数点在しています。
円覚寺、浄智寺、東慶寺など、見どころが沢山あるエリアですので、ぜひ、1日コースでこれらのお寺をまわると良いでしょう。浄智寺た円覚寺は別のブログに記事を書いていますので、下記をご覧ください。
関連記事
鎌倉 明月院は、決して大きなお寺ではありません。前身だった『禅興寺』は、関東十刹の一位までになった大寺院でしたが、廃寺になったあと残された明月院は、実に質素で楚々としたお寺です。それゆえに、その佇まいは奥ゆかしく、おしとやかな女性のような手触りを感じるお寺とも言えるでしょう。
そんな質素な明月院は、たくさんの見どころがあります。パートに分けてご紹介いたします。
まずは、庭園。
ちょうど、本堂の裏には『本堂後庭園』があります。しかし、こちらは残念ながら基本的には非公開で、季節限定の公開になっています。6月の花菖蒲の時期と12月の紅葉の時期のみ一般公開され、拝観料とは別に500円で庭園に入ることが可能です。
紫陽花の季節の6月は、ちょうど花菖蒲が見頃となっており、特別公開されます。
ぜひ、この時期に本堂裏庭園に入って、その美しい光景を堪能ください。
本堂後庭園は、たいへん見事な花菖蒲園と、美しい新緑に囲まれた美しい庭園です。そこには、紫陽花の挿し木が育てられており、大切に手入れされているからこそ、毎年見事な紫陽花のトンネルが堪能できるのだという事を感じます。
また、庭園付近には野生のリスたちが沢山お目見えします。軽快に木から木へと飛び移る野生のリスたちは、こころなしか社交的で、人馴れしているようにもみえました。明月院といえば、紫陽花と一緒に野生のリスも有名ですので、ぜひ、リスたちに会いに行ってみてください。
【PR】手作り結婚指輪・婚約指輪
また、もう一つ明月院の見どころといえば『悟りの窓』です。
明月院の本堂(方丈)には、御本尊である聖観音菩薩坐像が祀られています。この本堂(方丈)の前には丁寧に手入れされた枯山水庭園があり、こちらも見事です。
また、この本堂(方丈)には円窓があり、その奥に広がる庭園の新緑が、丸窓越しに眺められます。
この丸窓は『悟りの窓』と呼ばれ、悟り、真理、大宇宙などを円で象徴的に表現したものだそうです。

鎌倉 明月院には『鎌倉十井』の「瓶ノ井」(つるべのい)があります。内部が水瓶のようなふくらみがあることから「瓶ノ井」(つるべのい)と呼ばれているのだそうです。
江戸時代は、鎌倉は水質に恵まれない土地でした。そのため水質の良い水が湧き出す井戸は貴重な水源だったそうです。そのなかでも、水質が良く美味しいとされるいわれが残る、鎌倉を代表する10個の井戸の事を、鎌倉十井(かまくらじっせい)と呼びます。江戸時代には、鎌倉観光が盛んになったことで、名所旧跡を名数を使って紹介したのがはじまりと言われています。(瓶ノ井、甘露ノ井、星ノ井、底脱ノ井、扇ノ井、棟立ノ井、泉ノ井、鉄ノ井、銚子ノ井、六角ノ井)
明月院にある「瓶ノ井」は、いまでも使用できる井戸なのだそうです。明月院に行った際には、ぜひ御覧ください。
明月院には「明月院やぐら」という鎌倉最大級の「やぐら」があることで有名です。
「やぐら」とは、鎌倉時代中期〜室町時代にかけて作られた横穴式の納骨窟または供養堂。
明月院やぐらは、上杉憲方の墓といわれており、壁面に釈迦如来 、多宝如来と思われる像が浮き彫りされています。十六羅漢と思われる浮き彫りもあることから、「羅漢洞」とも呼ばれています。
明月院に行ったときには、明月院やぐらを見てみましょう。
鎌倉 明月院は6月の紫陽花の季節のみならず、通年通して美しく楚々としたお寺です。
紫陽花が終わっても、新緑に囲まれた静かなお寺は、私達の心を癒やしてくれます。北鎌倉観光では欠かせないお寺ですので、ぜひご参拝ください。
【PR】おすすめの鎌倉名物 おとりよせ
【PR】鎌倉プリンスホテル
\鎌倉といえばプリンスホテル/
【PR】お得に!楽しく!ホテルに泊まれる「旅のサブスク」